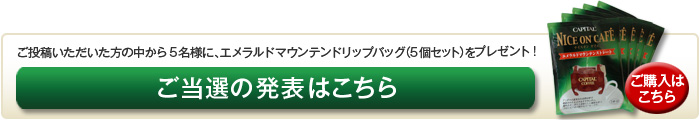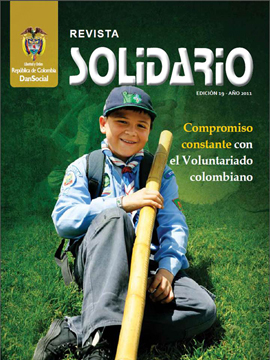|
|||||||||||||||||||||||||||
日本のボランティア元年といわれる1995年の阪神淡路大震災から18年、そして東日本大震災から2度目の3月がめぐってきます。だいぶ根付いた感のあるボランティアですが、昔から日本には「お互い様」の助け合い精神が生きていたのでは。そんな身近な視点から、あなたのボランティアイメージを教えてください。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
「あなたのボランティアイメージは?」ベストアンサーの5名様です。
体験を踏まえたお話と真摯なご意見を多数お寄せいただきました。 ボランティアということをこれだけ沢山の方が真剣に考えている 、それも自分に引き寄せて・・・とちょっと感動。日本のボラン ティア活動の未来を感じる貴重な投稿をありがとうございました。
●新潟県三条市 K.Aさん
仰々しく大々的にボランティアしていると聞くとなんだか恩着せがましい感じがするが、企業のHPなどをみてさりげなくボランティア活動をしていたと知るとへぇ〜そんなこともしていたのかと、感心する部分もあります。実際にどのような活動で、どんなことをいままでしてきたのかを知ることはその企業への関心も高まります。実際自分でもボランティアで活動したことはありますが、誰にもしたことは言わずさりげなくしています。
●神奈川県鎌倉市 K.Kさん
私は以前、障害者団体連合会の事務局でパート職員として働いておりました。その時に、知ったボランティアさんの存在。各作業所には、純粋なボランテイァさんがいらして、障害者の方と一緒に作業し、食事をし、サポートしていらっしゃいました。作業は、箱折りだったり、ボールペンの組み立てだったり、たわしを作ったり…と、地味な作業ですが、ボランティアさんの存在は大きく、不可欠です。特にお金に余裕のない福祉施設では貴重な人材です。自分で交通費を払い、昼食代を払い、作業所でお手伝いをするのです。とても立派だなと思いました。いつか自分もと思ってもなかなかすべてにおいて余裕がないと実行に移せません。そのうちいつか自分もそういうお手伝いができる状態になりたいと思ったものです。
●東京都葛飾区 M.Yさん
学生のころ、地域のためにゴミ拾いや老人ホームでのお手伝いなどのボランティア活動を実施していました。私にとってのボランティアのイメージは・・・「小さなお手伝い」です。大きなことをやる必要はなく、自分にできる小さなお手伝いをして、誰かの小さな助けになる、それだけで十分なんだと思います。
●兵庫県神戸市 Y.Rさん
自発的に無償で他者のために働くということは良いことだと思います。でも最近の学校教育の方針や、まじめ過ぎる学生さんとかだと、問題意識を高めたい(周りは自分たちよりも問題意識が希薄だと感じている)がために、「いかに多くの人々をボランティアに参加させるか」という方向に話がいきがちなので、違和感を感じます。もともとの語源であるvoluntaryは自由意志を持った自発的な行為を指していて、「〜すべき」だからしていることをボランティアとは言いません。いかにもありがちな「ボランティア」だけでなく、個々人が自発的に、思うような形で社会貢献することに対する評価がもっと上がってもいいと思います。彼らが思っているよりも実際は何らかのかたちで社会に貢献したいと思っている人はたくさんいるし、途上国支援や環境問題などにダイレクトに関われる職業は、ポストに対して志す人が多すぎる状態です。そういった格好良い仕事が出来る人は限られているし、需要がなく、人手よりもお金が足りないのが現状です。普通に企業で働いているサラリーマンでもお年寄りでも小学生でも、誰でも、強い問題意識や危機感などを持たずとも、ちょっと社会貢献したいなと言うときに気軽に出来るボランティアの形があればいいなと思いますね。楽しくなければ続かないですし、ボランティアというのは、語源の通り、人が人のために自分から何かをしようとする気持ちこそが重要なのだと思います。
●高知県高知市 T.Sさん
傾聴ボランティアのサークルに入り、自転車で通える範囲の一人暮らしのお年寄り宅を週イチで訪問しています。耳を傾けるだけのことですが、これがけっこう大変で…。でも私が来るのを楽しみにしていてくれている人もいるので、おかげで自分の存在価値を知ることにも繋がります。基本は【持ちつ持たれつ】常に対等であるべきだと思います!
エメラルドマウンテンオフィシャルホームページ:copyright (c) 2012 Andes Corporation, All Right Reserved. エメラルドマウンテンはコロンビアコーヒー生産者連合会(FNC)の登録商標です。 |